ビジネス展開と課題
東:続いて、当社がサステナビリティ経営を推進していくうえでの今後の方向性や課題についても、ご意見をお聞かせください。
当社では環境ビジョンの策定や水素関連技術の開発・導入など、将来を見据えた様々な取り組みを進めていますが、今後、持続的にビジネスを展開していくために必要なことや、現時点での課題・改善点についてご意見をお願いします。
社長:まずは、既に公表している環境ビジョンなどの方針にのっとり、着実に取り組みを進めることが重要だと考えています。水素関連技術についても、まだ本格的な普及段階には至っておらず、様々な技術的課題の克服も必要です。さらに当社のSEP船を活用した洋上風力関連事業などにおいては、今後の事業拡大に向けてお客様や社会のニーズをどのように的確に掴み取っていくか、その仕組みづくりにも課題があると感じています。
川田:脱炭素の取り組みがなかなか普及しない理由の一つに、コスト増があります。エネルギー事業者も利用者を増やすためにコスト削減に努めていますが、例えばリニューアブルディーゼル(バイオディーゼル)の場合、通常のディーゼル燃料に比べて足元では3~4倍の価格差があります。
当社では、各建設現場で発生する追加コストのうち、グリーン電力の導入費用に関しては工事原価負担とすることを今年4月より開始しました。バイオディーゼルについても、近い将来、工事原価負担とすることによって従業員の環境意識を高める考えであり、具体的な取り組みが順次進められています。実務の現場でしっかりと計画し、実行に移している点は、サステナビリティ経営における重要な行動だと感じています。
岩本:個人的に、今後の成長のためには海外展開が重要だと考えていますが、現地の方々に認められる存在になるには、数十年という時間がかかるでしょう。でも、当社が今後も持続的に発展し続けるためには、そうした覚悟を持って海外展開に取り組むことが不可欠だと思います。
田村:私も、積極的に海外展開の準備を進める必要があると思います。足元では、国内の建設需要が旺盛ですが、将来的には人口減少により需要が縮小する見込みですし、今から取り組んでいただきたいです。
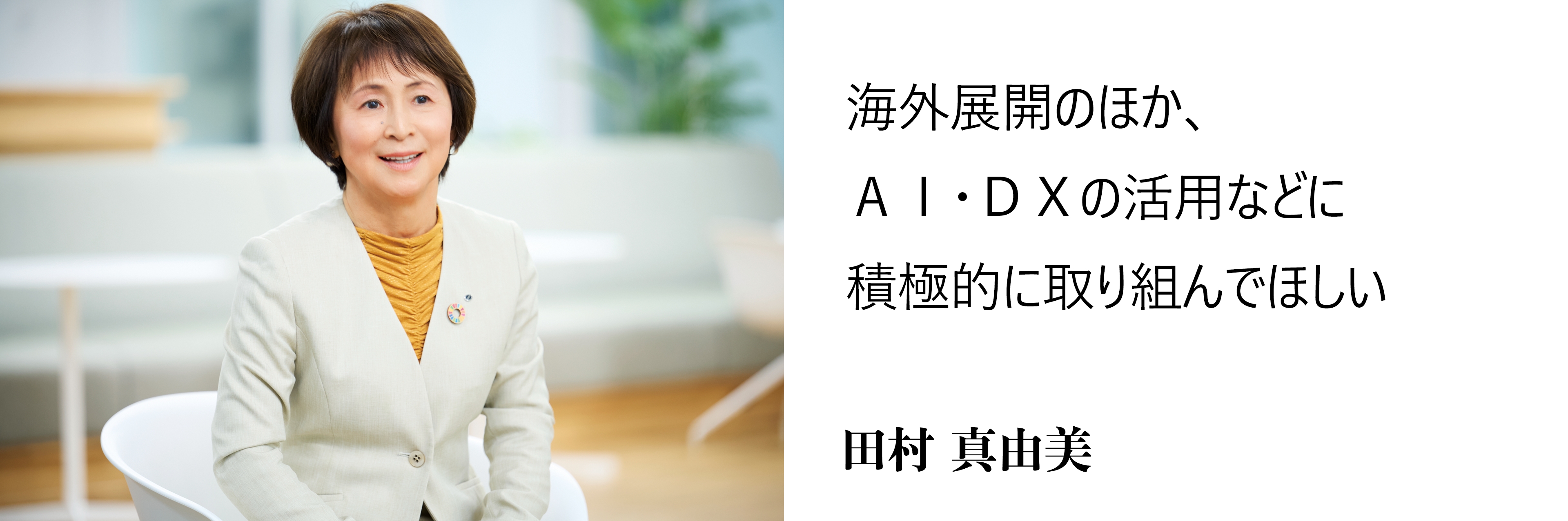
定塚:国内市場だけに依存するのはリスクがあるので、同感です。当社には優れた技術力があるので、その強みを今後は海外で活かしていくことができると思います。併せて、会社全体でグローバルな視点を持ち、様々な部門の知識や経験を持つ人が、年齢や性別、国籍に関係なく意見を交わしたり、国内外の拠点で活躍したりすることも大切だと思います。
また、当社は新しいビジネスの創出にも挑戦していますが、その原動力は従業員のアイデアですよね。そうしたアイデアを活かすためにも、若手が意見を言いやすい職場環境づくりが引き続き必要だと思います。当社は組織が縦割りになりがちなので、部門を超えたコミュニケーションや、誰もが自由に意見を出し合える風土をさらに醸成していくことが大切です。
岩本:組織の壁を超えるのは難しいことですが、これからは会社全体を意識して取り組んでいくといいと思います。
社長:はい。そこはきちんと意識して取り組んでいきます。
田村:それと、国内の労働力不足にもっと危機感を持ち、作業自動化の実現に向けた技術革新やAIの活用、DX推進などに積極的に取り組んでいただきたいです。加えて、社会的認知度を高める広報活動にもより力を入れるべきだと思います。
社長:そうですね。当社は真面目な社風なので「あえて対外発信するほどのことではないのでは」と思いがちな所もありますが、実際に取り組んでいることについては、積極的に社外に発信していきたいですね。加えて、「超建設」のマインドセットによる活動の成果が、社内外により分かりやすく発信されるようになれば、当社のイノベーション推進にも一層つながると考えています。新たな価値の創造に向け、進化を続けていきたいと考えています。

