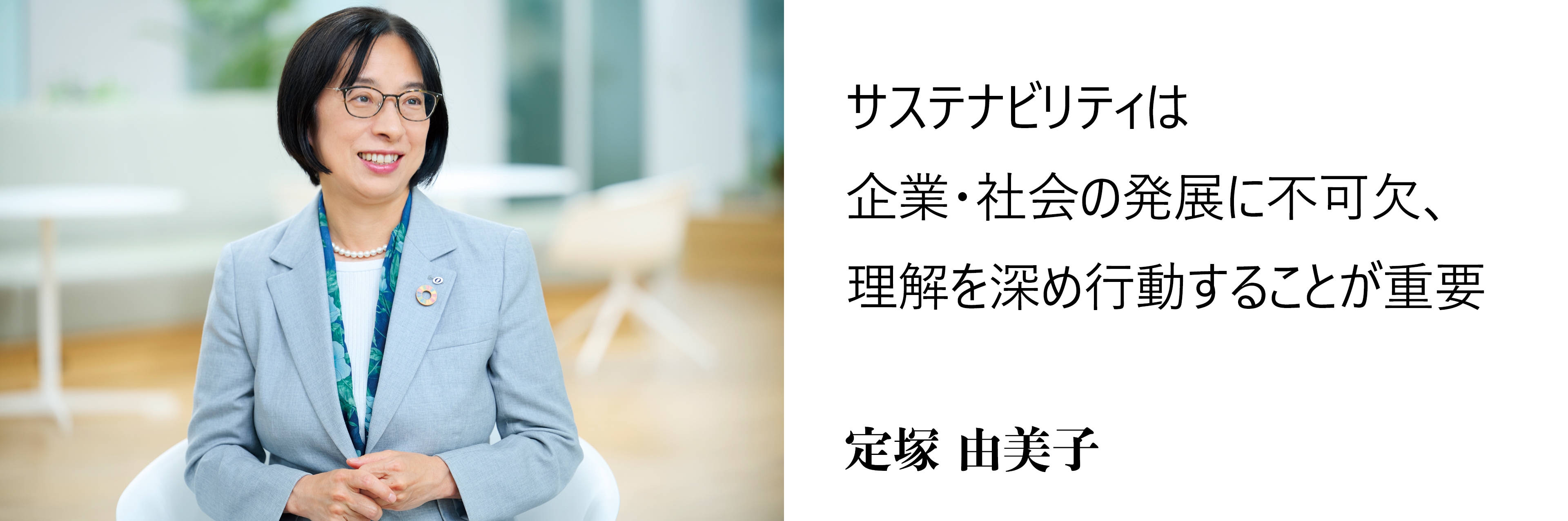世界の潮流
東:近年、サステナビリティに対する考え方が多様化する中、否定的な見方や慎重な動きも見られるようになってきました。特に米国では、ESGやサステナビリティの方針を見直す企業も出てきています。こうした状況の中で、当社がサステナビリティ経営を推進していく意義について、どのようにお考えでしょうか。
定塚:米国におけるESGやサステナビリティの見直しの動きは一時的なもので、今後も欧州を含め、世界的な潮流として進んでいくと考えています。サステナビリティは企業や社会の発展に不可欠なものですので、当社も理解を深めて行動につなげていくことが重要だと思います。
田村:サステナビリティ経営は、目的ではなく手段だと思います。そこを取り違えると、いわゆるESGウォッシュのように、見かけだけの取り組みや数値目標の達成に終始することになり、実態が伴わず利益にもつながらないという悪循環に陥ってしまいます。
岩本:何代にもわたり育まれ、受け継がれてきた会社のDNAは、たとえ時代が変化しても守るべきものです。そこはぶれてはいけない部分だと思います。
社長:私も、短期的な外部環境の変化に左右されるのではなく、「会社としてどうありたいか」という想いをしっかりと持つことが重要なのだと考えています。時代に合わせることも必要ですが、守るべき部分は今後もぶれずに継続していきたいと思います。
東:IRやSRの場では、「サステナビリティは社会課題へ取り組むことですが、企業収益にどのように結び付くのか」といったご質問をいただくことがあります。短期的な業績には反映されないケースも多いですが、なぜ腰を据えて取り組むことが重要なのか、お考えをお聞かせください。
社長:企業価値は業績だけで測れるものではないので、経済合理性だけでサステナビリティを論じるべきではないと私は考えます。私たちは、社会的な課題を自社だけの問題として捉えるだけでなく、日本や諸外国、さらには地球規模の課題として広く認識し、企業としてどのように貢献できるかを重視しています。こうした姿勢や取り組みの意義をステークホルダーに丁寧に説明し、積極的に発信していくことが重要だと考えています。
田村:サステナビリティ経営には多様性の確保が不可欠ですが、女性活躍推進などの取り組みの成果が出るまでには時間がかかります。将来的には、年齢や性別、国籍に関係なく、意欲ある人全員にチャンスがめぐる会社であってほしいと考えていますし、そのような環境の中で多様な意見が出されることでイノベーションは生まれてくるものと思います。私自身もそのような企業カルチャーが醸成されていくプロセスを、長い目で見守っていきたいと思っています。
川田:サステナビリティ関連のKPIは国際的な指標が多いですが、一方で国内の優良企業は、サステナビリティという言葉が生まれる前から、企業と社会の持続的成長を目指して取り組んできました。これは「幸せの追求」という意味でも、継続していくべきものだと思います。そのうえで当社独自のKPIを設定し、より実効性のある取り組みにつなげていけばよいのではないでしょうか。