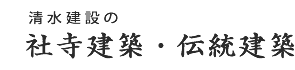都市計画に伴う移設等「長谷院本堂」
長谷院は寛永8(1631)年、港区虎ノ門に草創。嘉永3(1850)年に麹町からの延焼により被災し、その後改築されましたが、大正12年の関東大震災で再び被災。昭和12年に本堂、庫裡が再建され現在に至っています。今回の工事では、都市計画に伴い、墓地とともに本堂、庫裡を江戸川区へ移転、新築されることになりました。

施工データ
| 名 称 | : | 長谷院本堂 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 東京都江戸川区 |
| 設 計 | : | プランツアソシエイツ |
| 規 模 | : | 延床面積 878 m2 地上3階 |
| 構 造 | : | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 |
| 竣 工 | : | 2004年7月 |
建設における課題
高精度施工の実現
旧本堂の解体に伴う古材等を再利用し記憶の継承を図る、主体構造は鉄骨造でALC板(蒸気処理をした軽量気泡コンクリート)を採用する、外壁はセメント系漆喰調美装左官仕上げにする等の設計意図を実現するため、高精度の施工が求められました。
軟弱地盤
計画地は地下水位が高く、地盤も軟弱なため、工法に検討が必要でした。
狭い搬入路
広い敷地に比べ搬入路が狭く、また一方通行もあり、車両の進入には規制がありました。
墓地販売への影響
建物の着工より半年前から竣工した墓地の販売が行われており、購入者や参拝者が多く、行事等も行われるようになったため、音や振動等の規制を受けることになりました。
課題に対するシミズの設計・技術対応
設計意図を生かすための施工法の選択
構造体の鉄骨を化粧材として見せる、大きな外壁面を左官工の手作りによる漆喰調で仕上げる等、高精度の工法を実現するため、細部にわたり納まり図を作成。モックアップ(詳細模型)で施工法を確認しながら建物を作り上げました。
軟弱地盤での不具合防止
基礎を沈下させないようにするため、基礎地盤工事に使う砕石には厚みをもたせ、十分に固めて使用しました。また、高い地下水位に対処するため、設計者に協力を依頼し、基礎梁の高さを浅くして水による不具合が出ないようにしました。
計画的な車両配置
大型車両による資材の搬出入時には、1台ごとに車両の大きさを確認。近隣等にも迷惑がかからないよう計画的に車両を配置しました。
隣接墓地での行事等への対応
お客様と連絡を密に行い、ときには工法を変えるなどして、音や振動等に関するクレームがないよう対処しました。