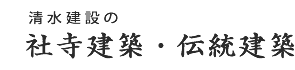戦災等による被災後の復興等「穴八幡宮隨神門」
嘉永2(1849)年、初代清水喜助により竣工した高田八幡宮(現・穴八幡宮)隨身門(ずいじんもん)は、昭和20(1945)年5月の空襲によって焼失しました。
その後、平成元(1989)年から始められた境内全域の整備計画の一環として、約半世紀ぶりに隨神門(ずいしんもん)として再建されることになりました。

施工データ
| 名 称 | : | 穴八幡宮隨神門 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 東京都新宿区 |
| 設 計 | : | 清水建設 |
| 規 模 | : | 延床面積 25.18 m2 地上1階 |
| 構 造 | : | 木造 |
| 竣 工 | : | 1998年8月 |
建設における課題
歴史的資料がわずかであったこと
再建に際し、歴史的資料の収集に力を入れましたが、残っていたのは、神社所有の宝永元(1704)年に描かれた立面図1枚と当社所有の初代清水喜助が描いた立面図1枚、そして、戦前に撮影されたモノクロ写真数枚だけでした。
課題に対するシミズの設計・技術対応
現存している資料を最大限に尊重し、現代人にも共感と感銘を与えられる造形意匠を目指しました。
黄金比の採用

全体のプロポーションには1:1.6の黄金比を採用。同時に細部の割り出しには、日本古来の木割を用い均整の取れた形を実現しました。
先端技術により「規矩術」の設計を再現
軒廻りは、総反り、反出し勾配という日本の大工技術の最も高度な「規矩術」をCADで再現し、構造面においては実物大の実験を行いました。
室町中期の仕口を改良
仕口は、飛鳥時代から江戸時代までの先例を調査。その中でも最も秀逸と言われている室町中期の仕口に改良を加え、耐震性、耐久性に優れた構造を実現しました。