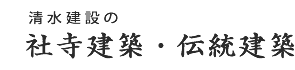土地有効利用等「清水寺本堂」
清水寺は、日本橋馬喰町にあった明暦3(1657)年に明暦の大火(振袖火事)で被災。その後、東京都台東区の現在地に再建されました。今回の工事では本堂等の老朽化対策とともに、敷地と容積を活用し、本堂、庫裡、客殿、納骨堂、共同住宅を合わせ持つ新しい施設として建て替えられることになりました。

施工データ
| 名 称 | : | 清水寺本堂 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 東京都台東区 |
| 設 計 | : | 清水建設 |
| 規 模 | : | 延床面積 3,502 m2 地下1階 地上2階 地下1階 地上11階 (共同住宅) |
| 構 造 | : | 鉄筋コンクリート造、 鉄骨鉄筋コンクリート造(共同住宅) |
| 竣 工 | : | 1997年2月 |
建設における課題
異種用途の混在
地下1階は納骨堂、地上1階と2階は寺院、3階から11階は共同住宅、という異種用途が混在した複合建物であるため、より正確で緻密な設計と施工計画の作成が求められました。
地上2階までの複雑な配置関係
地下1階から地上2階までは、本堂や庫裡等とともに、共同住宅のエントランス等が配置されているため、エレベーターや立体駐車場、階段等の開口部や床の段差が非常に多く、施工の難しさが懸念されました。
課題に対するシミズの設計・技術対応
構造物を一つにした容積活用設計
限られた敷地内での複雑なゾーニングを、よりわかりやすい動線で結ぶことを基本にレイアウトを設計。異種用途の空間を一つの構造物とすることで、地下を含む寺院部分とともに、容積を活かした高層共同住宅の建設を実現しました。
緻密な施工順序と施工計画の作成
資機材の運搬方法や重機のアプローチ方法、作業者の動線、施工順序や施工計画等を緻密に計画。床の段差や開口部がある中で安全性と作業性を確保し、共同住宅建設と寺院建築の同時進行をスムーズに実施しました。
“らしさ”をそれぞれに表現した外観
外観は、寺院と共同住宅という全く異なる要素をそれぞれ素直にデザイン。寺院は寺院らしく、共同住宅も同じようにし、あえて統一させないことで、多くの商店と住宅が立ち並ぶ既存の街並みになじむよう配慮しました。