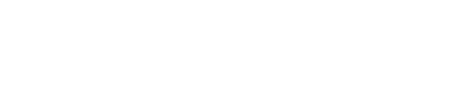2023年3月14日
Vol.73 東京木工場で新年拝賀式、初午祭を行いました
東京木工場は1884(明治17)年に清水組の木材加工場として江東区木場に開設され、以来、関東大震災や戦火での焼失を乗り越えて工場設備を拡充してきました。
東京木工場の施設群は、いずれも築50年以上を経過していることから、順に解体し、「木の文化・技術・魅力」の発信拠点として、全面建て替えプロジェクトが進められています。
建て替え前の東京木工場で今年も伝統行事の「検尺式」と「初午祭」が執り行われました。
安全と品質向上を祈念する「検尺式」
2023年1月4日に、東京木工場の新年拝賀式において、協力会社の会である清木会とともに、「検尺式」が行われました。
検尺式とは、年始に検尺棒と呼ばれる、長さを測るための基準となる物差しをつくり、祀ることで、その年の安全と品質向上を祈念する行事です。検尺式は検尺の儀とも呼ばれています。
現在の検尺式では、検尺棒となる2本の桧材に鉋をかけて表面を整え、墨つぼと墨さしを用いて検尺の基準となる線を引きます。最後に2本の検尺棒を水引で束ね、末広(扇)を取り付けて壁に立てかけます。
検尺式の手順






商売繁盛、災難除けを祈願する「初午祭」
2月最初の午の日である2月7日に、東京木工場の事務所棟屋上にある兼喜稲荷大明神で商売繁盛、災難除けを祈願する初午祭を行いました。



検尺式の歴史
本社で行われる手斧始め(ちょうなはじめ)の儀式にならい、戦前から行われていた検尺をつくる仕事始めの一連の作業を、「検尺の儀」として木工場での新年拝賀式の中に正式に取り入れたのは、1965(昭和40)年からです。
当初、検尺棒を仕上げていく所作には20名ほどが携わる大規模な儀式でしたが、時代に合わせ1972(昭和47)年以降は現在の形式に簡略化。儀式では、法被を着用するようになり、さらに参加人数も「末広がり」の吉言から8名となりました。以来今日まで検尺の儀として継承しています。