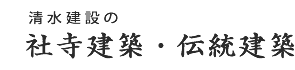本妙寺の壮麗な高麗門の再建
清水家の菩提寺である本妙寺に山門が竣工しました。
本妙寺は、とげぬき地蔵(高岩寺)の近くの豊島区巣鴨五丁目にある法華宗陣門流の東京別院になります。
本妙寺には、当社の物故社員慰霊塔のみならず遠山の金さんのモデルの遠山景元、囲碁の歴代本因坊、剣士の千葉周作など、著名人のお墓が多くあります。
既存の山門が小さく、工事や緊急用の車両が境内に進入できないことから、今回山門を大きく建て替えることになりました。
新しい山門の間口は柱間4.8m、総高さ6.9m、扉の内法3.9mになります。

【正面】
今回、大型の山門となるため、構造は鉄筋コンクリート造(RC造)としました。
木割り(部材の比例寸法)としては伝統木造の高麗門と同様のものとし、壮麗で格調高く見えることを狙いました。
宮大工とともに実際の寸法の現寸図を作成していきます。

現寸図から型枠をつくっていきます。
伝統木造の形状をRC造で作る場合は、軒反りなど3次元的な曲面もあるため、伝統木造の知識を持った専門の型枠大工が作ります。

軒裏の垂木は、部材が小さく、形状もわずかに反っていて本数も多いので、工場であらかじめプレキャストコンクリート(PC)で製作しました。

PCの垂木からは鉄筋が伸びていて、型枠に組込み、屋根のコンクリートを打設すると一体になります。

コンクリート打設終了後、上棟式を執り行いました。

次にその型を元に、石膏型を作ります。
その型の内側に薄くセメントとガラス繊維を混ぜたGRCを塗り込んで、固まったら型からはずし完成です。

出来た木鼻は、人力で運び、本体の門にボルトでしっかりと固定しました。

仕上はコンクリートの上に塗装になります。
コンクリートに下地調整パテを塗っては磨くという工程を重ねて平滑にしてから塗装をおこなうことにより、表面は漆塗りのような光沢をもつようになります。
それぞれが高度な専門職人の手仕事に依っています。

扉は木製とし、欅の無垢材を使用しました。
扉の化粧板は厚さ3cmもあります。
10枚の化粧板は1つの大きな原木を割って得たため、連続感をもった木目の揃った扉とすることができました。

扉は片側で高さ3.9m、巾2.16m、重量約600kgもあります。
重く大きいため、吊り込みはフォークリフトで行いました。

門の金物にはこの本妙寺と墓地に眠っている方にゆかりのあるモチーフからデザインをおこしました。
扉の留め金具については、法華宗の宗紋の六本桜と、墓所のある遠山の金さんの桜吹雪を元にデザインし、桜色の石を埋め込みました。

また、八双(はっそう)金物は、鋭い形で千葉周作の剣を、また、碁石と同じ寸法の黒白石を埋め込むことにより、本因坊の囲碁を表しました。

巣鴨の近くへお寄りの際は、本妙寺にお寄りいただき、著名人のお墓に御参拝し、往時に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

施工データ
| 名 称 | / | 本妙寺 |
|---|---|---|
| 所在地 | / | 東京都豊島区 |
| 設 計 | / | 清水建設 |
| 規 模 | / | 地上1階 |
| 構 造 | / | 鉄筋コンクリート造 |
| 竣 工 | / | 2015年7月 |