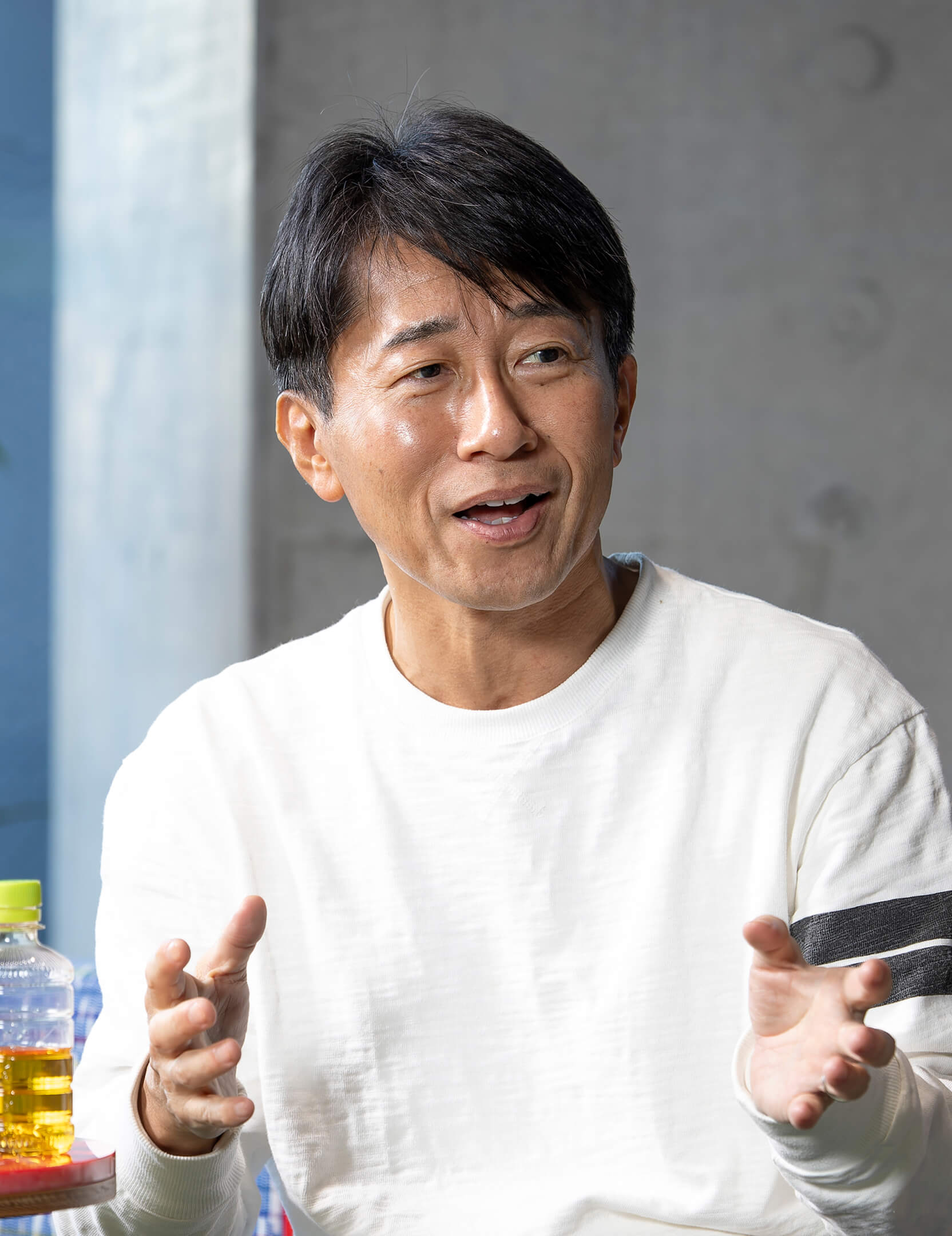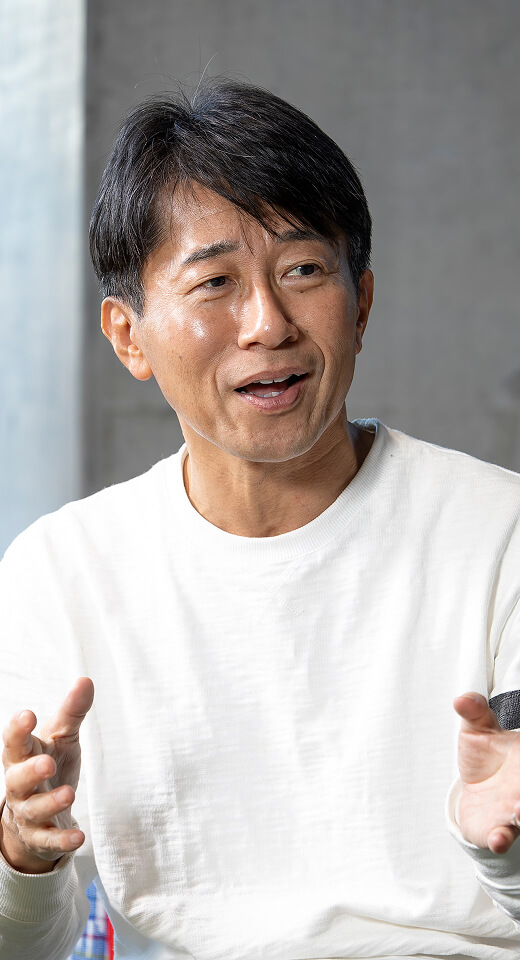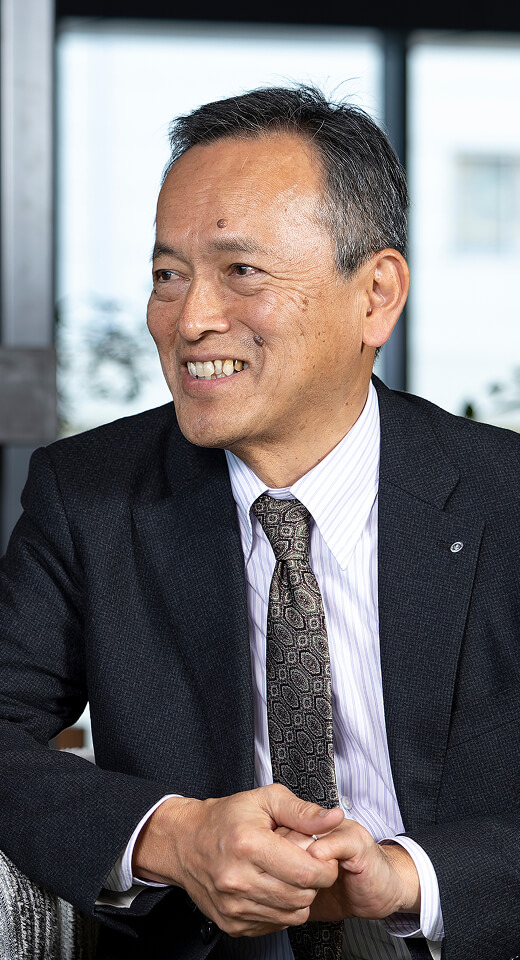ABOUT STORY
社会課題の解決や、新たな事業創出の手段として注目を集める「オープンイノベーション」。
NOVAREにおいても、多様なパートナーとの共創によって次々と新たな価値が誕生しています。
なぜ今、時代はオープンイノベーションを求めるのか-。本記事では、オープンイノベーションの本質に迫るべく、新規事業家の守屋実氏をNOVAREにお迎えし、NOVAREエグゼクティブコンダクター大西と対談いただきました。
スタートアップと大企業の共創によって陥りがちな「やるやる詐欺×できるできる詐欺」とは?そしてNOVAREが目指すべきものとは。 ぜひ最後までご覧ください。
こちらの記事は特別対談
「未来を共創する力:後編」になります。
2025/04/22
5 min read
3. スタートアップと大企業が共創するための条件とは
やるやる詐欺×できるできる詐欺に陥るな。
中島:スタートアップと大企業が連携する意義、そして成功に導いていく方法についてはどのようにお考えでしょうか?
守屋:時代の変化が激しい中、大企業が変化を先取るスタートアップと組むのはメリットが大きく、自然な流れだと思います。また、スタートアップにとっては、大きなリソースを持つ大企業と協業するメリットが大きいのは当然のこと。
その中で、逆に成功しない例を考えてみると、大企業が「やるやる詐欺」、スタートアップが「できるできる詐欺」をしているパターンがあるんじゃないかと。その典型は、大企業が少子高齢化や気候変動、SDGsといったビッグワードだけを掲げ、「やるやる!」と協業相手を募集しているようなケースです。99%の確率で、その実態として確固たる具体的な事業創出の意志がないため、スタートアップがピンポイントな技術を武器に「できるできる!」と手を挙げても、結局判断がつかなかったり、最終的に大企業が求めるものに合致しなかったりする。このミスマッチの主犯は大企業です。「やること前提」でないから、協業の呼びかけが曖昧になり、曖昧だからスタートアップは正しく手を挙げることができないのです。「やること前提」での協業募集なのであれば、どの課題に対して、どんな目標を設定していて、その実現のために自社では不足しているものがあり、だからそれを「オープンイノベーション」する、という展開になって当然のはずなのです。
例えば、DENSOのオープンイノベーションには、まさにお手本となる事例があります。DENSOは「Car to Car」というコンセプトを掲げ、車のすべての構成部品を原材料に戻し、次なる車の製造へと循環させることに挑戦しています。ただこの時に、「過酷な使用下でも壊れないようにあらゆる技術を結集した」ということが、ブーメランになってしまいました。「どんな時も絶対に剥がれない接着」を目指したこれまでの努力が、「早く安く精緻に剝がそうとしたら剥がせない」というデメリットとなって返ってきた状況です。そこでDENSOは、自社技術の具体的課題を開示し、課題をクリアできる企業を広く募ったのです。大企業がこういった情報を開示することは非常に勇気のいる難しい決断です。しかしDENSOは事業計画の年数までも開示し、設備または知財を提供してもらってDENSOの設備内に組み込み、全世界への販売を目指すことを宣言しました。その結果、全く関係のない町工場から手が挙がったのです。そこまで情報を開示すれば、逆にそれができる企業しか集まらず、やるやる・できるできる詐欺には陥りません。
他にも、僕がフェローを務めているJR東日本スタートアップの事例で言うと、キオスクで働く人員を確保できず店舗の撤退を余儀なくされる状況の中、無人キオスクやウルトラ自販機という新たなコンセプトを掲げ、つくれる会社を広く募集したところ、多くのスタートアップが手を上げてくれました。大企業が解像度120%で開示することで、スタートアップも解像度120%で手を上げることができるのです。良好な関係はそうやってつくられていくのだと思います。

大西:建設業界の場合、建設業会社の数が多すぎると言われつつも、あまり淘汰されず現代になり、大手5社がしのぎを削る状況でした。他社と技術共創することを躊躇する風潮がありましたが、人財不足も深刻化する中で、「競争する部分はそのまま」に、「共創できる部分は共創」しましょうという動きが活発化しています。
例えば施工関連技術のうち、ロボットやIoTアプリに関する研究開発は、複数の建設会社や協力企業でコンソーシアムをつくって取り組むなど、役割分担が進んできています。日本でロボットを開発できる企業が何十社とあるわけではないので、優秀な企業と本気になって取り組めば開発も早く、いろいろな企業への波及力も高まります。業界の中で技術を囲い込むのではなく、他社と一緒になって徹底的に課題を掘り下げる意識・風潮は確かに高まってきていると感じます。
守屋:ゼネコンが技術を引っ張り、社会をビフォーアフターで変えた具体的事例があると、他のインダストリーにも大きな影響を与えるのではないでしょうか。清水建設がそんなリーダーシップを持ってイノベーションを成し遂げ、社会に勇気を与えることができたら、かっこいいですよね。
できるだけ象徴的な実例だと良い。業界的すぎると一般の人たちが良く分からず、あまりにも一般的すぎると業界にとって意味がない。経産省などを巻き込んでゼネコンがつくる共創の未来、などの思い切ったキャンペーンも良さそうです。
大西:スタートアップ側もそんなキャンペーンがあると入り込みやすくなりますよね。
守屋:想いをどこに向けるかだと思います。例えば建物という「製品」は、世の中のあらゆる製品のなかでも、最大級にデカい製品です。だとすると、その「廃棄」はこれまた最大級のすごい量になる。この桁外れなゴミ問題に何か課題を置いて、大手ゼネコンでどう解決するかを競い合い、補い合い、そのビフォーアフターの事例を公開するとか。
中島:大西さんが思うビフォーアフターのアフター、理想の思い描く姿を聞きたいです。
大西:建設は一品生産で、二度と同じものはありません。同じように見えてもすべて違い、我々は日々新しいことに取り組んでいます。しかし世の中に対するインパクトやイノベーションでいうと、「広くあまねく」普及することこそ、真のイノベーションだろうと思っています。先にお話した『慈雨』や、『Hydro Q-BiC』もその道半ばですが、守屋さんがおっしゃった成功体験をNOVAREで積み重ねていきたい。ここまでやった、というものをまずは実現するべく、頑張ろうと思います。

4. SHIMZ NEXTが描く未来とは
社会や国を動かす、大きな力になると信じて。
中島:オープンイノベーションの実例として、「SHIMZ NEXT」にも触れておきたいと思います。「SHIMZ NEXT」は、NOVAREを舞台に清水建設が主体となって国内外のスタートアップなどと共創するイノベーション創出プロジェクトです。大西さんに始動時のお話をお聞きしたいです。

大西:「SHIMZ NEXT」始動時に社内課題として多く挙がったのは、CO2排出量やエネルギーに関わる問題でした。全世界の総CO2排出量の約42%が建設物由来であるというデータがあります。しかし、これまで建設前の見積書には、建設生産過程でのCO2排出量が記載されていませんでした。これには数千以上に及ぶ膨大な精算見積項目の仕分け作業が必要であり、人力での計算・集計では膨大な時間が掛かってしまうためです。しかし、CO2データ分析システムの開発を手掛けるスタートアップのゴーレム社と共に取り組んだ結果、建設生産過程で生じるCO2排出量を精算見積データから自動算出できるプラットフォーム「SCAT(SHIMZ Carbon Assessment Tool)」の開発に成功しました。
この他にも、チームメンバーの所在やオフィス内のコミュニケーションを可視化する位置情報システムをフィンランドのHaltian社と開発するなど、スタートアップとの共創は続いています。これらの技術はすべて、開発して終了ではありません。次のステップを常に考え、最終的には国を動かすような大きな力になると信じて進み続けなければならないと考えています。
中島:一つの壁はクリアしたものの、社会全体に広くあまねく使っていただくことが本当のゴールですね。
大西:建設業は本来一品対応で、広めるという考えがなかなか根付いておらず、そこは発想の転換が必要だと思っています。本社や各現場などでももちろん取り組んでいますが、NOVAREで心をまっさらにして挑戦したいですね。
守屋:人は人に影響を受けるので、一品をつくることにこだわる人が多ければ皆が同質化してしまうでしょうね。逆を言えば、別の考えを持つ人と関わればそちらに影響を受けて変わっていきます。新しい血が混ざる場所がNOVAREであり、そういう場所をつくることで自然と交配が進むのではないでしょうか。
大西:はい、まさにそういう場としてここをつくりました。

守屋:結局、本業で成果を出した方が評価され、出世できるという評価制度では、優秀な人財は流出してしまうと思います。外に出た方が儲かるので。だから大企業で、ミドルリスク・ミドルリターンみたいな評価保証制度があると良いですよね。スタートアップはハイリスク・ハイリターンで失敗した時にゼロですが、大企業はローリスク・ローリターンの文化が根強い。その中間として、新規事業に挑戦する人財にミドルリスク・ミドルリターンの仕組みを提供できれば、日本らしい価値をもっと生み出していけるのではないでしょうか。
5. オープンイノベーションを成功させるには
本業の常識で、新規事業をとらえない。
中島:多くの新規事業を創出されてきた守屋さんですが、オープンイノベーションを成功させるにはどのような要素が重要だとお考えでしょうか?
守屋:オープンイノベーションはあくまで手段であり、実際にはクローズドイノベーションでも良いと思います。でも、きっと今はオープンである方がやりたいことができる。クローズドであれば、今までにも実現できる機会はあったはずなので。だからこそ、オープンイノベーションを成功させるには「やること」を明確にしておく必要があります。
中島:実際、守屋さんが行ってきた事例を踏まえ、乗り越えた術を教えていただきたいです。

守屋:今日本では、ベンチャーキャピタルが年間で1500~1600社ほどに投資を行っているのですが、実際の毎年の上場企業数は100社ほどとなっています。しかも、そのうちの20~30社はずっと頑張ってきた中堅企業だったりします。つまり、いわゆるスタートアップの上場確率は1500~1600社中の70~80社、ざっくり言えば1/20ということになります。
一方、大企業が新規事業の現場に求めている事業規模は、本業の規模に引きずられて非常に大きくなりがちで、上場できるような規模感だったりします。
だとしたら、大企業の新規事業の成功確率も、ざっくり1/20でもおかしくないはずですよね。だから、清水建設で取り組んでも、19/20は失敗して当たり前なんです。
起業家は当たればデカい。だから過酷な生存確率の中でも頑張れるんです。でも、大企業ではそうはいかず、本業の習い性で「失敗は許されない」という評価になっている。この考え方の違いが、大企業が頑張れない部分の要因になっていると思います。
僕自身、新規事業家という肩書で活動していますが、新規事業だけを36年間やっています。事業開発にアサインされて、2〜3年で結果が出せずに別の部署に異動させられるというシステムでは、成功するのは難しいでしょう。本業の常識で新規事業をとらえてはいけないんです。
中島:NOVAREは今まさに成長途中ですが、大西さんから見てオープンイノベーションを成功させるために重要だと思うことは何でしょう?

大西:現在、NOVAREにはさまざまな人財が集まり、イノベーションの種が次々と生まれています。守屋さんのおっしゃる通り、せっかく本社と違う挑戦ができる環境があるのだから、NOVAREならではの文化を醸成していかねばならないと思います。
そんな挑戦の意思を示すものとして、私たちが掲げたのが「Change and Chain〜勇者であれ〜」というVISIONです。NOVAREを構成する一人ひとりが、変化を恐れず、人とつながり続ける勇者であることを示していきたい。文化とは一朝一夕でできるものではありませんが、結果は苦しかったが取り組んだ事実は認められる、という文化をつくっていくことが大事だと感じています。
守屋:具体的な事業がちゃんと利益を出す、というシンプルな事例が一個でもできるとみんな目の色が変わります。その一個の事例が出ない限りは綺麗な言葉で踊らされているだけで、現実問題に対して目の色は変わりません。
僕がミスミにいた時、事業の成果に応じて報酬が青天井に支払われるという人事制度がありました。利益分配制度の一環として、ある人が複数の事業を一度に成功させ、1億円のボーナスが支給されたことがありました。今から20数年前の話ですが。その時社内に激震が走り、全員が経営者目線に変わるのを肌で感じました。極端な例を出しましたが、華々しいヒーローやヒロインをつくることは非常に有効だと思います。
中島:わたしもヒロインになりたいです!
新規事業創出において2〜3年で結果を出さなくてはと思っていましたが、失敗して学ぶことを繰り返し、清水建設の中で新規事業のプロとなる人財が何十人、何百人と育てば、素晴らしい財産になるんじゃないかと思いました。
守屋:はい、そう思いますし、それは可能だと思います。清水建設で働く人の0.1%が新規事業人財に変われば、それだけで十分に大きな一歩になると思います。また、世の中には僕のような新規事業家は何人もいるわけで、そういった人たちがNOVAREに集えば、その一歩が二歩になり、二歩が三歩になり、そして歩幅が増してやがてジャンプできる日が来ると思います。NOVAREがそんなイノベーションを加速させる場であってほしいですね。
6. 終わりに
新たな社会価値の共創を目指して。
中島:総括としてまず大西さんからのお話と、最後に守屋さんからNOVAREに対するエールをもらえたらと思います。
大西:まず今日話を伺って、やってみなければ結果は出ない。やるしかない、と非常に背中を押されました。また、オープンイノベーションで外部との共創を図ることはもちろんですが、新規事業のプロを育てるためには、内部改革も同時に進めるべきだと改めて感じました。例えば、現在既に社内にあるコーポレートベンチャリング制度(起業家公募プログラム)をさらに発展させ、支援体制を充実させるなど、さまざまな可能性が考えられます。NOVAREはまだ生まれたばかりなので、いろんな意見をいただいて、意欲・能力のある人が挑戦できる環境をつくるべく動いていきたいと思います。

守屋:せっかくNOVAREという場があるのだから、やるしかないですよね。ここは学校ではなく、僕たちは学生ではない。ここは実際のビジネスの場であり、僕たちはビジネスパーソン。これだけ恵まれた環境でやらない人は、人生最大のチャンスがあってもやらないという選択を取り続ける人です。そしてこの場での挑戦は、必ず周囲にも影響を与えると思います。本日お話して新たなイノベーションが生まれていく予感を大いに感じました!
大西:私は現在の清水建設を、強い縦糸の集合体が膠(にかわ)で固まっているような集団だと思っています。それをNOVAREが横からほぐし、一人ひとりの挑戦を後押しして、より社会のニーズに応えられる組織にしていきたいと思います。NOVAREは清水建設の単なる出島ではなく、会社全体に影響を与える組織です。そのための成功物語を積み上げていきたいですね。
守屋:いけると思います!例えばJRがそうだったのですが、本業は鉄道輸送業であり、スタートアップと組むことに反発もありました。しかし、一つの成功事例をつくり出せたことで流れが変わったんです。
どんなに縦糸が凝り固まっていても、着実に一歩ずつ進めていけば、必ず変わります。まずは一つの成功事例を、NOVAREでつくり出しましょう!

守屋 実氏
新規事業家。ミスミを経てミスミ創業者田口弘氏と新規事業開発の専門会社エムアウトを創業。複数事業の立ち上げと売却を実施、2010年守屋実事務所を設立。新規事業家としてラクスル、ケアプロの創業に副社長として参画。2018年、ブティックス、ラクスル、2か月連続上場。博報堂、JAXAなどのアドバイザー、内閣府有識者委員、山東省人工智能高档顧問を歴任。近著、「新規事業を必ず生み出す経営」(日本経営合理化協会出版局)、「起業は意志が10割」(講談社)、「DXスタートアップ革命」(日本経済新聞出版)。
大西 正修
清水建設 副社長執行役員
NOVARE エグゼクティブコンダクター、イノベーション担当、フロンティア開発室長
中島 由美(ファシリテーター)
NOVARE ベンチャービジネスユニット