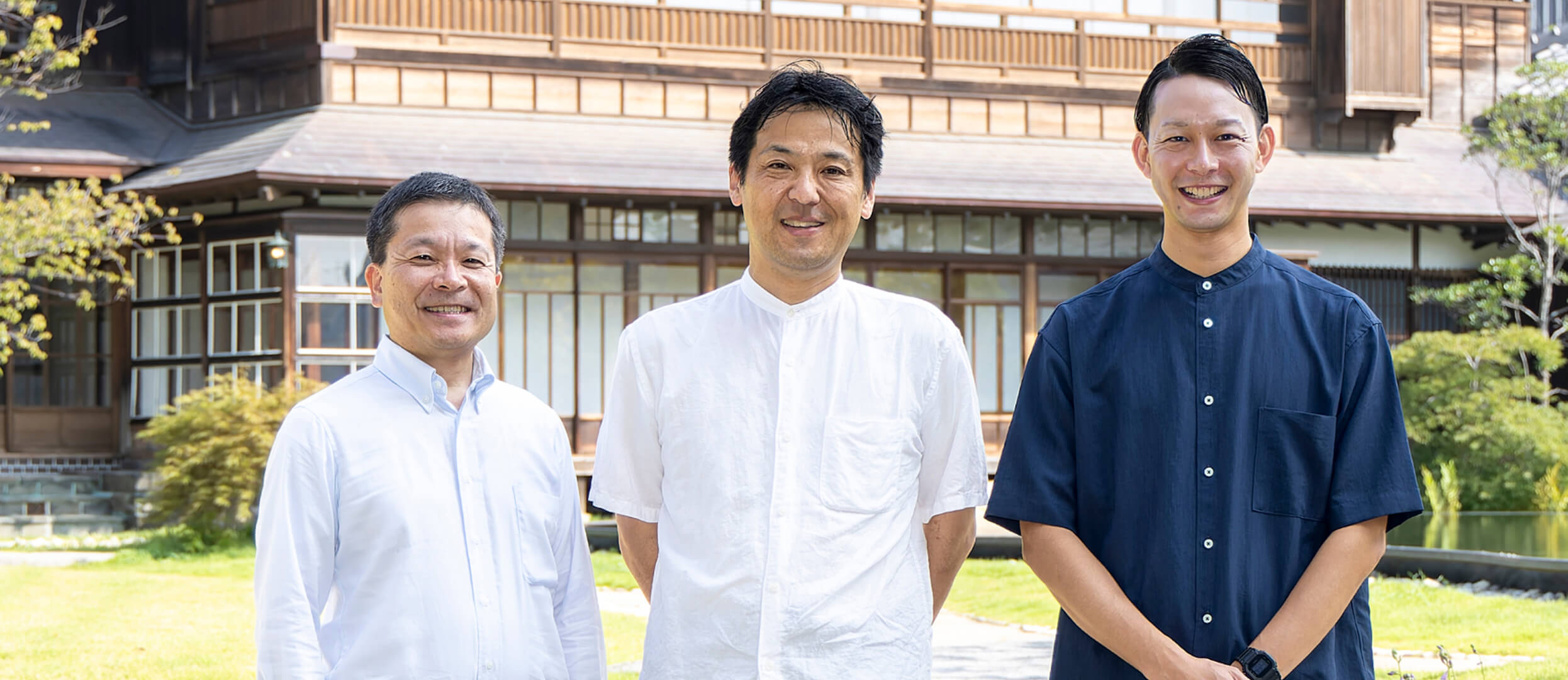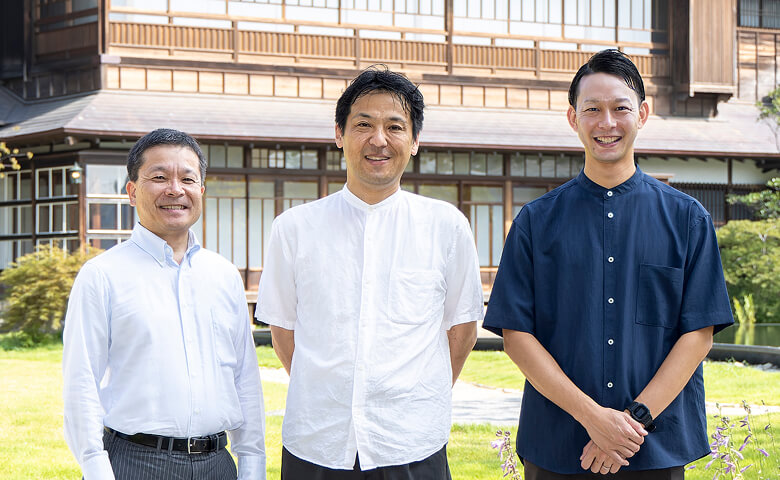2025/09/16
6 min read
ABOUT STORY
NOVAREの旧渋沢邸に実装された自動火災検知放水システム「慈雨」 。
今回は開発に携わった3人のそれぞれの言葉でプロジェクトを熱く語ってもらいました。
WHY
(なぜ):文化の多様性を維持する
守るべき価値を、
未来につなぐために。
なぜ今、慈雨が必要なのか。なぜ今、清水建設が取り組む必要があったのか。
慈雨開発のリアルな経緯を教えてください。
牧住:個人的な想いからお話しすると、そもそも私はまちづくりに関心があって。谷中地区(台東区)のまちづくりに関わる当事者でもあるのですが、都市の法制度のあり方に違和感を覚えていました。記憶に新しいのは、古い町並みを残すために都市計画道路を廃止して地区計画を立ち上げた時のこと。結果として道を50cmだけ広げることになり、ただその50cmを確保するために、お寺の塀や町屋の庇は壊さないといけない事態に陥りました。
こういったケースでは、目的が法の遵守になってしまい、本来の「町並み保全」の観点がないがしろにされています。壊さなくてもよいものを壊すのは本末転倒。消防のために必要な道路幅員を6mと決めつけるのではなく、もっと本質から考え直せば、横幅が細い消防車両を開発するとか、消火栓の改良や、街全体にスプリンクラーのようなものを設置するなど、分野を横断した総合的な解決策を講じられるはずだと感じたんです。
私たちは建設会社なので、もちろん新しいものを建てていく価値を知っています。しかし一方では、古いものを守り続ける尊さも知っている。町並みを残す考えと、建築する考えとの両面で考える必要があります。町並みを守るため、現状の法律という一側面からではなくもっとトータルで考えたい。そんな想いを抱いていた時に、ここNOVAREの話が持ち上がり、旧渋沢邸の移築が決まりました。

重盛:貴重な建造物である旧渋沢邸は「絶対に燃やしてはならない」。じゃあどうすれば守れるのか、という議論が始まった時、本気でガラスの箱に入れる案もありましたよね。見学者も建物内部の見学はしない、外から見るだけの置物にする方が最も災害リスクが低い、と。しかしやはり旧渋沢邸を体感するためには建物内部の見学が欠かせない。この矛盾をどう解くか、というのが大変でした。
野竹:日本には自然と建物が調和した文化的景観を「名勝」として指定する制度などがあります。こうしたわが国固有の景観を次世代につなげ、継承していくイノベーションに貢献したい、と以前から思っていました。だから今回、牧住さんと重盛さんから熱い想いを聞いたとき、「よし、やってやろう!」と思いましたよ。

重盛:やはり、実際にものを見る、その場で体感する、というのは代え難い経験ですよね。私も京都へ旅行に行って、寺社仏閣を実際に観ると、やはり感動しましたね。今後デジタル化が進んでいっても、きっと人は旅行に行き、体感することをやめたりはしないと思います。だからこそ、実際に見て感動できる建造物は守りたいんです。
牧住:ものを「つくる」ことと「守る」こと。二項対立のように聞こえてしまうかもしれませんが、未来に価値をつなぐという意味では同じです。しかし、つくらなくてもよいものまで「つくる」のはどうなのか。つくるだけだと資源が無駄になります。だから、「守る」ことも重要だと思うんですよね。そこにどれだけ私たちの想いや技術をつぎ込んでいけるか、ということです。
重盛:とはいえ、かなりの難題でしたよね。旧渋沢邸は30年近く青森にあったので、まずは移築することで変化する事柄とその対策を一つひとつ書き出し、災害のリスクを評価することから始めました。その結果、「屋外の壁面を消火する」という対策に至ったというのが、慈雨の始まりです。
HOW
(どのように):木造の弱点を最新技術で克服する
炎が消えた瞬間に感じた、
安堵と喜び。

では、実際どのように慈雨開発に至ったのでしょうか?
重盛:木造建築の弱点として、やはり燃えやすいために火災の早期発見が不可欠、ということが挙げられます。これまでの防火システムの多くは、炎の大きさが一定程度大きくならないとセンサが反応しないため、屋外での火災発生を早期に発見できないことが課題になっていました。
牧住:炎の広がり方に「軒の形」も関係しているんです。軒は上からの水を外壁から離すように作用しますが、逆に外壁を立ち上る炎に関しては、軒が受け止めてしまいます。
重盛:その軒下の火災に対して幅広く放水し、水が壁面を流れ落ちることにより、壁面火災を鎮圧できないか、とメンバーで仮説を立てながら消火システムの構築を進めていきました。壁面に着火し、軒下で熱が溜まり、火災が一気に広がる状況を理論上イメージはできます。実際に消火システムが有効なのか証明するには検証実験が不可欠で、これが大変でした。
まずはパートナー企業の工場に、旧渋沢邸 表座敷の軒下壁面を実物大模型で作成しました。実際に燃料を焚いて壁面火災を再現すると、軒下に広がる炎の勢いは予想以上。防護服を着て間近で立ち会いましたが、ものすごい熱で、正直恐怖を感じるほどでした。映像では伝わりきらないほどの勢いで、木造建築の火災の恐ろしさを身をもって体感できたことが、開発にも大きく影響しました。
軒下壁面の実物大模型に点火・放水する実験を行い、火災の拡大を抑制する性能を検証(7秒)
牧住:本当に、軒下を伝う炎の横の広がりと勢いはすごかったですね。そしてその炎が、慈雨の放水で一気に消えていった。
重盛:それを見た瞬間、「我々の仮説は間違っていなかったんだ!」と防護服を着たまま手を取り合って感動しました。パートナーのみなさん含め、居合わせたメンバーは拍手喝采でしたよね。事前実験は重ねていたのですが、実際自分の目で結果を見るまでは半信半疑だったんです。しかしあれだけメラメラと燃え広がった炎に有効だったというのは、予想以上の安堵と喜びでした。

牧住:思わず握手したよね。木は少し湿っているだけでも燃える速度が遅くなると検証できましたし、慈雨の開発という目的を超えて、得るものが大きかったと感じます。
野竹:そうそう、さらに新しい発見もありましたよね。木材が燃えて炭化していく、そのスピードに関しても遅くなることがデータとして残ったのは大きかったですね。
また、ノズルの選定も苦労しました。普通の放水銃だと水の勢いが強すぎて、木造建築を壊す恐れがあったんです。様々な放水手法を実際に検証して、最終的な扇形の放水手段に至りました。
重盛:それから、旧渋沢邸に対してのノズル配置計画も一筋縄では行かなかったですね。放水の角度や強さのデータは取りましたが、それをどう設計に落とし込むかはものすごく難しくて。最終的には3Dデータを使って、三次元的に建物と放水をとらえながら組み立てていきました。この設計プロセスの簡略化も今後の普及の鍵になると考えています。
WHAT
(何を):AIを用いた自動火災検知放水システム「慈雨」
慈雨の本質は、
技術ではなく「想い」
慈雨普及の現在地、今取り組まれていることを教えてください。
野竹:極端な話を言うと、普及の鍵は牧住さんのような人がたくさん集うことだと思っています。建物を守る手段の一つが「慈雨」。この建物を「守りたい」という想いのもとに人が集まれば、どうやって守るか、何をすべきかを議論する機運が生まれ、そこでいろいろなアイディアが出てくると思うんです。昨今は、建物を建てる→法令遵守→消火設備設置という順序で考えがちですが、まずは何のために遺したいのか→どうやって守るのか、という原点に戻って手段を提案していければと考えています。
重盛:設計の立場から言うと、普段の新築設計で「法文に則って消防設備を設置する」以上に踏み込むのはまず難しいです。でも慈雨開発を通して、本来防災って「何のために」から考えるべきなんだ、と身に沁みて感じました。近年で言えば、能登半島地震で輪島の町の一部が消失する、という痛ましい出来事もありましたが、無人の放水システムがあれば消失を防げたのではないかという議論もあります。実際には、慈雨じゃなくてもいい。けれど慈雨のような考え方があれば、町並み保全に貢献できるはずです。

牧住:これまでのお話を聞いていただくと分かる通り、慈雨って単なる技術じゃなくて「想い」なんですよね。旧渋沢邸を守りたい、文化遺産を、町並みを守りたい、と願う一人ひとりの想いが集まって価値が生まれていく。そしてそれがしっかり経済を動かして行くところまで辿り着きたいです。
開発メンバーのアイデアで決まった「慈雨」というネーミングにも、この想いが象徴されていますよね。

重盛:「慈雨」は、日照りが続いた後に大地に降り注ぐ恵みの雨、という意味合いです。今回の早期自動火災検知放水システムには直接関係するものではないのですが、なぜかイメージがぴったり合うんですよね。それが我々も不思議で。みんな納得のネーミングです。
NEXT STAGE
:未来への可能性
人の情熱を検知し、
「新しい建設」を共創。
慈雨の次のステップはどのように考えていますか?
牧住:慈雨は完成されたパッケージ品ではなくて、目的に合わせて柔軟に適応していく覚悟も用意もある、というのは強調しておきたいです。
例えば今は屋内早期火災検知システムの開発にも取り組んでいます。屋内のスプリンクラーは天井に設置されていますが、炎は下から上に広がる。その際に天井に水を噴霧しておけば、天井の燃え広がりが抑制されます。現在は、この下から上へ放水する自走式の消火設備の企画を立てたり、早期発見につながる画像検知やガス検知システムの開発を進めたりと、やるべきことを一つずつ積み重ねている状況です。
この記事の読者のみなさんへ、メッセージをお願いします!
野竹:「慈雨は想い」という話がありましたが、やはりこの想いを渡せる方と一緒にスケールさせていきたいです。それには人の出会いがどうしても必要で、その熱い想いを引き寄せられる場がNOVAREだと思います。火災の早期検知ではないですが、我々も対話の中から相手の情熱をしっかり検知し受け止める感度を磨いて、もっといろんな方と語り合いたいです。

重盛:旧渋沢邸への実装をきっかけにはじまった慈雨ですが、NOVAREは技術のショールームではないんですよね。常に変わって行く、進化させて行く場がNOVARE。僕自身も「WHY(なぜ、何のために)」から考える設計者として、未来を見据えた次の一手を提案し続けたいです。
牧住:NOVAREは、今まであたりまえとされてきた建設の流れをもう一度見つめ直して、社会のニーズ、物事の本質から考え直せる場です。
以前のやり方や成功例にならっていくと、どうしても本当に必要なものがだんだんずれてきてしまう。だからこそ慈雨の開発は「守りたい」という思いから出発できたことが良かったと思いますし、つくって終わりでもない。建築の中に潜む無数の可能性を見つけて、つないで、本当に社会に必要とされる新しい建設をつくっていきたいと思います。

牧住 敏幸(まきずみ・としゆき)
一級建築士/日本建築学会文化施設小委員会 幹事/日本火災学会会員/日本大学理工学部 非常勤講師
個人プロジェクトとして「貸はらっぱ音地」を主宰(日本建築士会連合会まちづくり賞)。各種 PFI・PPP プロジェクトや木質建築、データセンターから教育・文化施設まで多岐にわたる設計に携わり、公共建築賞をはじめ、グッドデザイン賞、ウッドデザイン賞など受賞。新たな建設のあり方を目指す施設「温故創新の森 NOVARE」では日経ニューオフィス大臣賞、BCS 賞等を受賞。
重盛 洸(しげもり・こう)
一級建築士/建築設備士
事務所ビル、商業複合施設、生産施設等の設備設計業務に従事。2019 年より当プロジェクト(温故創新の森 NOVARE)の設計室に配属となり、2024 年の施設本格稼働に至るまで設備設計およびシステム開発に従事し、現在も施設運用をフォロー。当システム開発にて令和6年度火災学会技術賞および令和6年度総務省消防庁優良消防用設備等表彰を受賞。
野竹 宏彰(のたけ・ひろあき)
一級建築士/博士(工学)/日本火災学会常務理事(総務担当)/日本防火技術者協会(JAFPE)理事
建築防火分野をはじめ、災害レジリエンスに関する研究開発に従事。高層病棟の火災時避難安全システムの開発、火災時のエレベーター利用避難に関する研究、大規模避難所のフェーズフリーな運営体制の構築に関する研究などを担当。